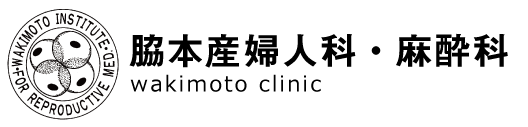分娩予約と費用について
wakimoto clinic

分娩予約について
分娩予約の方法
当院では無痛分娩を多数実施しているため、安全上の理由で分娩件数を制限しております。
子宮内に胎嚢が確認できれば、受付で分娩予約をお取りすることが可能です。
当院でお配りしています分娩予約申込書と分娩予約金3万円を医院の受付にご提出いただき、予約申し込みを完了します。
お電話での分娩予約は受け付けておりません。定数になり次第、締切りますのでご了承下さい。
1.予約申込金の3万円は退院の際に分娩費用に充当して清算させていただきます。
2.予約申込金は、流産及び当院医師の指示による転院や母体搬送など医学的事由の場合には全額返金いたしますが、それ以外の理由によるキャンセルはキャンセル料として3万円申し受けますので返金致しかねます。
慎重にご検討のうえお申し込みください。
出産費用
おおまかな目安として、自然分娩が53~55万円、無痛分娩が61~70万円程度(個室)となります。
時間外・休日・深夜の分娩は時間外加算33,000円が別途かかります。
厚生労働省のサイト「出産なび」をご参照ください。
近隣の分娩施設との出産費用の比較が可能です。
- ●
- 初産・経産とも出産日を0日目として産後4日目退院です。
- ●
- 時間外:平日・土曜日6時~8時、平日18時~22時、土曜日12時~22時
休日:日曜日・祝日、年末年始の休診期間
深夜:22時~翌6時
※時間外、休日、深夜の規定は健康保険の規定に準じております。
無痛分娩の費用
通常の分娩費用(53~55万円)+麻酔費用 75,000円(経産婦)/ 150,000円(初産婦)
初産婦さんは39週前後、経産婦さんは38週前後での計画無痛分娩となります。内診所見を参考に決定いたします。
麻酔は硬膜外麻酔が基本ですが、状況により脊椎麻酔併用硬膜外麻酔(CSEA)とすることもあります。
分娩進行が極めて早い場合は脊椎麻酔のみで無痛分娩とすることもあります。
いずれの方法でも費用は変わりません。
硬膜外カテーテルを留置したタイミングあるいは脊椎麻酔で麻酔薬を投与したタイミングで費用が発生します。
帝王切開の費用
65万円前後(術後6日目退院です。)
お部屋の空きがあれば7~8日目位まで延長可能です。(入院費が別途かかります。)
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払い制度について
出産の際に、多額の現金をご用意していただかなくて済むように、平成21年10月から「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が始まりました。
当院での出産の際は、この制度をご利用いただいております。
直接支払制度とは
対象になる方は支給額は50万円です。このうち産科医療補償制度に12,000円が充当されますので、残りの488,000円を出産費用に充てさせていただきます。
- 1.
- 出産する方が加入されている医療保険に、当院が手続きを代行して出産育児一時金を請求し、入院費用に充てさせていただきます。
病院は代行手数料はいただきません。(家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます) - 2.
- 退院時に出産費用の不足額を当院会計窓口にてお支払いただきます。
- 3.
- 帝王切開などの保険診療を行った場合は、3割の負担金をお支払いいただきますが、一時金をこの際のお支払に充てることもできます。
- 4.
- この制度を利用される方は、入院手続き時に同意書への署名をお願いいたします。
もし、この制度を利用されない方は、お申し出ください。その場合は、出産費用の全額について退院時にお支払いただくことになります。
出産を予定する方へのお願い
- 1.
- 入院時にマイナ保険証(又は保険証)をご提示ください。
また、入院後、保険証が変更された場合には速やかに変更後のマイナ保険証(又は保険証)をご提示ください。 - 2.
- 妊婦健診等により、あらかじめ帝王切開など高額な保険診療が必要とわかる場合は、加入されている医療保険に「限度額適用認定証」等を申請し、会計の際にご提示ください。
但し、マイナ保険証をご利用の場合は不要です。
限度額適用により、一般的に3割の窓口負担が「80,100円+かかった医療費の1%」に据え置かれます(所得により異なります)。 マイナ保険証を使用されない方で、認定証を入院時にお持ちでない方は、退院時までにご入手ください。